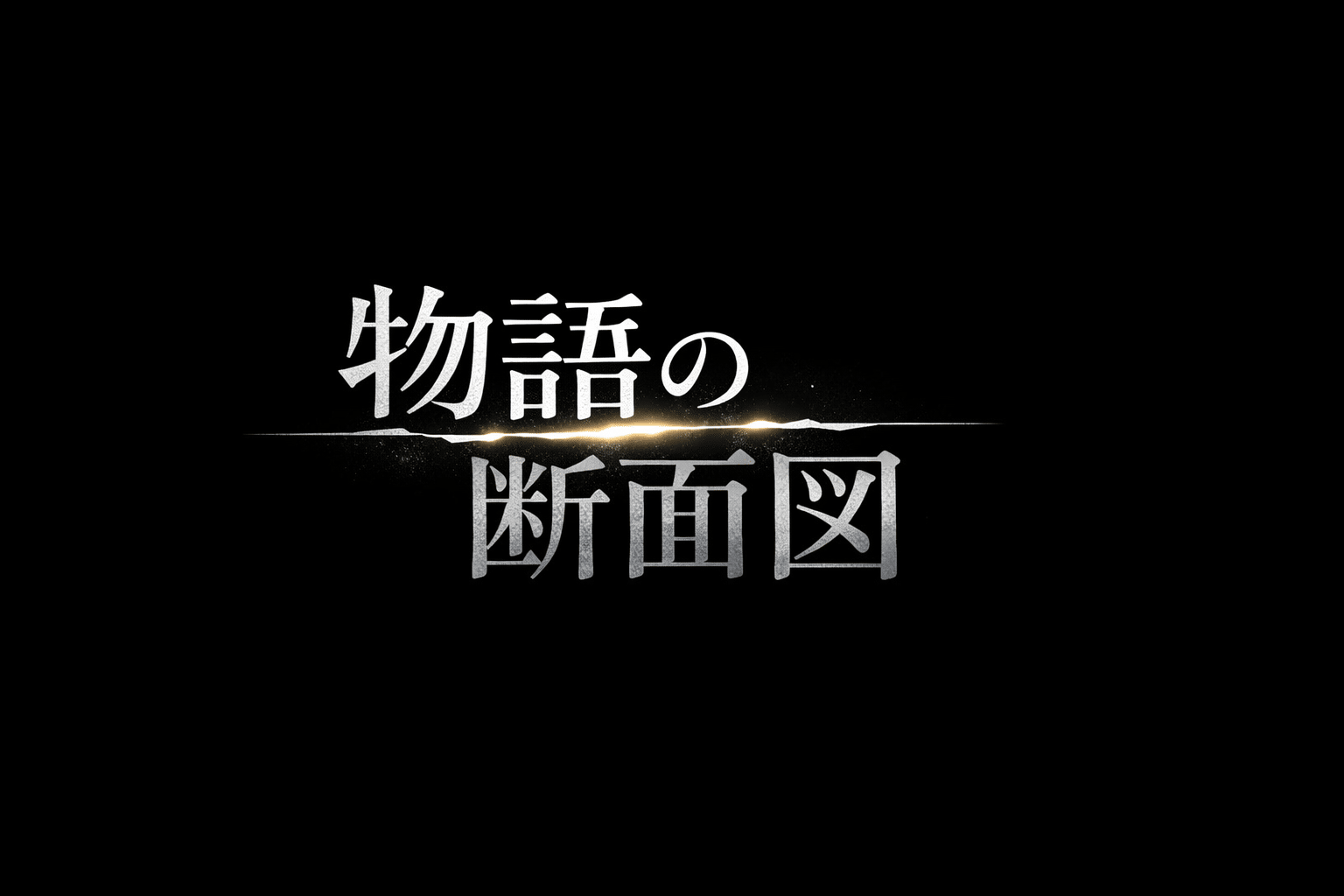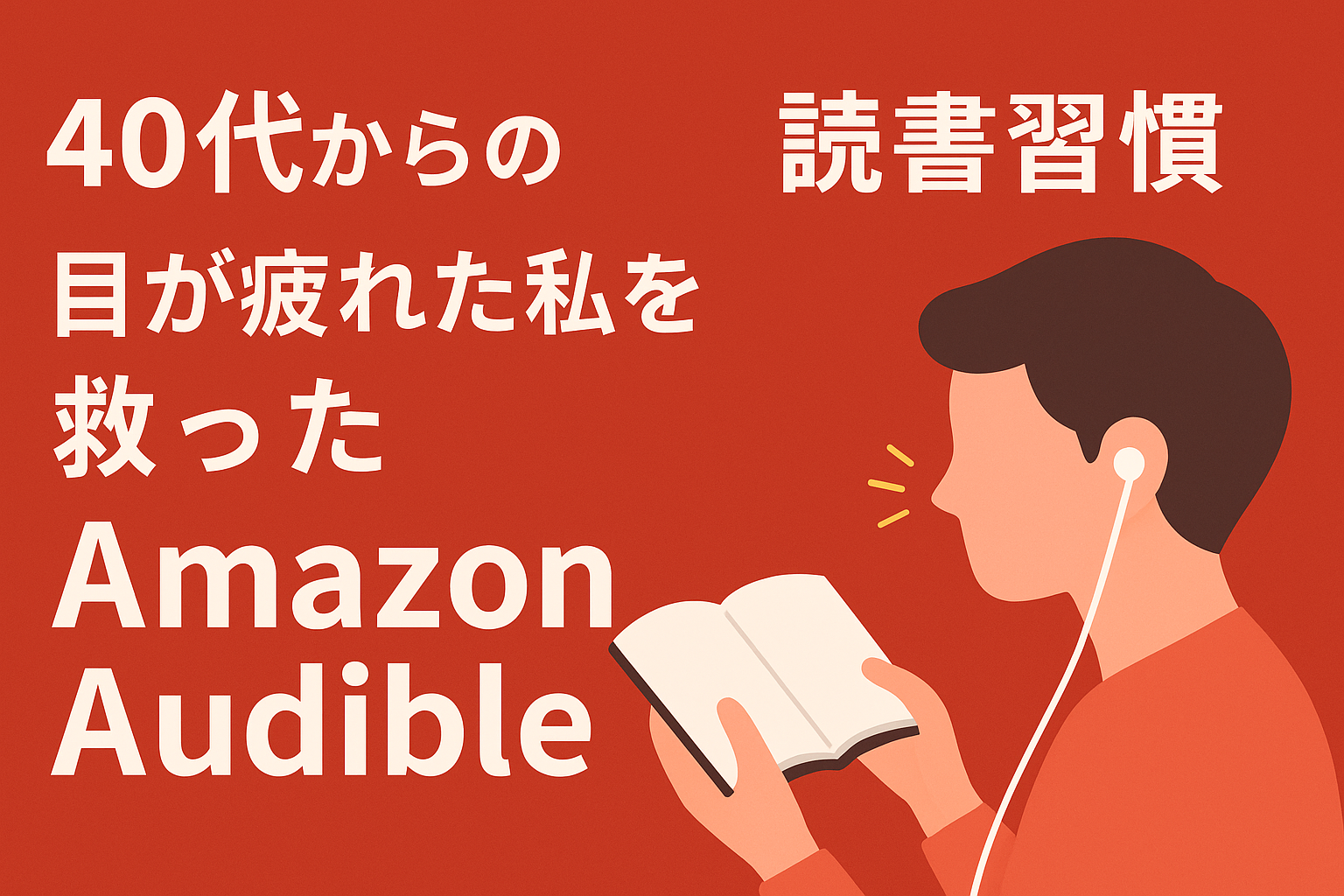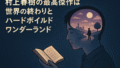高校2年の冬。布団の中で、僕は一冊の本を開いた。
タイトルは――太宰治『人間失格』。
その夜のことを、僕はいまだに鮮明に覚えている。
ページをめくるたびに、まるで自分の心の奥を暴かれていくようだった。
気づけば時計の針は午前5時を過ぎていて、それでも手を止めることができなかった。
太宰治の言葉は、十代の僕にとってあまりにも鋭く、そして痛いほど優しかった。
■ 『人間失格』とは何か ― 太宰治が描いた「人間の弱さ」
『人間失格』は、太宰治が1948年に発表した長編小説。
「恥の多い生涯を送ってきました。」――この冒頭の一文から始まる物語は、主人公・大庭葉蔵の手記という形で進んでいく。
葉蔵は、人との関わり方がわからず、常に「笑顔の仮面」をかぶって生きてきた男だ。
心の中では怯え、孤独を抱えながらも、他人に嫌われないようにと、道化を演じ続ける。
その結果、彼は少しずつ社会から、そして自分自身からも切り離されていく。
太宰治は、この葉蔵という人物に「自分自身」を重ねたと言われている。
『人間失格』は単なる小説ではなく、太宰の告白であり、叫びであり、日本文学史上もっとも痛切な“独白”なのだ。
太宰治文学の特徴は、共感だ。読者はみな、“自分もどこかで同じように生きている”と、思ってしまうのだ。友達と笑い合いながらも、心の中ではいつも「本当の自分を知られたくない」と怯えていた10代の頃。太宰の言葉は、そんな僕の仮面の裏を見透かしていた。
※ちなみに世界文学の中で一番印象が似ているのはドスエフスキーの『地下生活者の手記』だ。前者は感傷的であり後者は論理的であるが、不思議とどちらも同じ主人公のような気がする。※興味がある方は是非読んでみてください。
■ 高校生だった僕に刺さった一文
「幸も不幸もありません。一切は過ぎていきます。」
この一文を読んだ瞬間、胸の奥で何かが静かに崩れた。
あの夜、『人間失格』を読み終えたとき、外はもう白んでいた。カーテンの隙間から差し込む朝の光が、やけにまぶしく感じられた。眠気よりも、心の奥に新しい何かが芽生えていた――それは「人は弱くてもいい」という、ささやかな希望だった。
僕は、『人間失格の世界観』という重たいハンマーで頭を殴られたが、一方で興奮していた。面白くない日常が変わった瞬間だった。大げさに言うと、つまらない世界が終わった。大事な何かに気づいてしまった。
「もう誰に合わせる必要もない。僕は自由だ!」
不思議と、そんな感情を抱いた。
当然のように、その日、学校を休んだ。「学校なんて休んでもいい。一切は過ぎていく」。ただ眠たくなっただけかもしれないが、その時は本気でそう思っていた。
■ 太宰治の言葉が教えてくれたこと
『人間失格』は、絶望の物語のように見えて、実は“生きることの意味”を問いかける作品だと思う。
太宰治は、人間の醜さや弱さを否定するのではなく、むしろそれを受け入れる勇気を書いていた。
葉蔵が完全に壊れていく過程の中で、逆に“人間であることの尊さ”を知った気がした。
あの夜から、僕は文学に目覚めてしまった。日本人作家はもとより、海外の古典も読み漁った。あの夜『人間失格』を読んでいなかったら、ここまで文学好きにはなっていなかったのは間違いない。僕は文学のなかに人間の真実を探していた。それは父のような母のような人類の先輩である誰かの言葉を通して、自分を見つめ直す時間になった。
太宰治の人生を集約したような小説『人間失格』は、僕の中で今も静かに息づいている。
■ まとめ:人生を変える一冊に出会う夜
- 『人間失格』は太宰治の代表作であり、人間の弱さを真正面から描いた名作
- 10代の頃に読むと、共感と衝撃が何倍にも響く
- 「人間失格」という言葉は絶望ではなく、“人間であること”への再定義
もし、あなたが今、誰にも言えない孤独や不安を抱えているなら、ぜひ、太宰治『人間失格』を開いてみてほしい。眠れぬ夜に読むその一冊が、あなたの人生を静かに変えるかもしれない。
ただ「太宰治を読む」それが資本主義の末期のような現実世界で生きる現代人にとって良いことか悪いことか、未だに僕にはわかりません。その判断は、あなたに委ねます。
人間失格はAmazon Audibleで気軽に聴けます。→1か月無料体験はコチラ