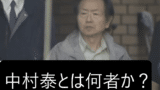もう何度見たかわからない映画に、『ゆきゆきて、神軍』がある。
ゆきゆきて、神軍は、日本映画史において最も賛否を呼び、最も恐れられ、そして最も忘れられないドキュメンタリー映画だ。
監督は、原一男。主人公は、元日本兵の奥崎謙三。※奥崎は、天皇パチンコ事件や伝説の政見放送でも有名だ。
この映画は、ただの「戦争の記録」ではない。戦後日本が無意識に封印してきた“責任”を、暴力的なまでに掘り起こす映画だ。表のテーマでは戦争責任を追及し、裏では最もセンセーショナルな日本軍による「人肉事件」という戦争のタブーを真正面から追及していく。物語が進むごとに明らかになるのは、ニューギニア戦線で実際に起きたとされる人肉食の疑惑だ。奥崎謙三が戦時下では当たり前の事実を執拗に掘り起こし、「白豚」「黒豚」「代用豚」という隠語の意味を平和ボケした戦後日本人に問い詰めていく。
本記事では、映画のあらすじと背景を整理しながら、日本軍人肉事件とは何だったのか、なぜこの作品が今なお高い評価を得続けるのかを解説する。
映画の概要(基本情報)
- 公開年:1987年
- 監督:原一男
- 主演:奥崎謙三
- ジャンル:ドキュメンタリー映画
- 上映時間:約122分

『ゆきゆきて、神軍』が表に掲げるテーマは一見シンプルだ。
「なぜ戦場で部下が処刑されたのか?」
しかしその問いは、やがて天皇制・軍隊・国家・戦後民主主義そのものへと拡張していく。
さらには日本軍が当たり前に人肉を食べていた事実が暴露されていく。
あらすじ|「責任者を探せ」という狂気の旅
太平洋戦争末期、ニューギニア戦線。奥崎謙三は、上官によって二人の兵士が“処刑”されたと確信している。
戦後40年。彼は元上官たちを訪ね歩き、カメラの前で問い詰める。
- なぜ殺したのか
- 誰の命令だったのか
- 天皇は責任を取らないのか
何かを恐れているかのように真相を語るのを拒む元上官たちに対し、奥崎の追及は、やがて暴力を伴う異常な行動へとエスカレートしていく。
観客は次第に分からなくなる。
正しいのは誰か?
狂っているのは誰か?
奥崎謙三という存在|英雄か、狂人か
奥崎謙三は、単なる「変わり者」ではない。戦後日本を代表するアナーキストである。
- 天皇制を真正面から否定
- 国家を加害者として告発
- 自身の暴力行為も隠さない
彼はこう言い切る。
「天皇は戦争犯罪人だ」
これは、日本社会において最大級のタブーである。
映画は彼を肯定もしない。否定もしない。
ただ、逃げ場のない“剥き出しの存在”として提示する。
中村が無言のテロリストだとしたら、奥崎は雄弁なテロリストとも言えるだろう。
原一男の演出
原一男は「客観性」を捨てた。
- 止めない
- 編集で中和しない
- 観客を守らない
カメラは、暴力・狂気・矛盾・不快感のすべてを丸裸で記録する。
それはドキュメンタリーというより、一種の思想実験である。
後年、原一男は「カメラを意識して奥崎の行動がだんだんエスカレートしていった」と語っている。たしかに映画内でも常に奥崎はカメラを意識していた。例えば「そこはカメラがあるから、こっちに座りなさい」と言っている場面もあった。
なぜ今も問題作なのか
『ゆきゆきて、神軍』が危険なのは、戦争そのものよりも戦後日本の“無責任”を暴くからだ。
- 戦争は終わったことにされている
- 責任者は曖昧にされた
- 個人は「被害者」に回収された
奥崎謙三だけが、「お前は何をしたのか?」と問い続ける。
この問いは、今もなお有効である。
人肉事件の追及|「白豚」「黒豚」「代用豚」という言葉の正体
『ゆきゆきて、神軍』が単なる戦争責任追及映画では終わらない理由―それは本作が、日本軍による「人肉食」事件を真正面から扱っているからである。
奥崎謙三がニューギニア戦線で追及するのは、部下処刑だけではない。
彼が執拗に問い詰める核心は、次の一点だ。
「あの肉は、何の肉だったのか?」
戦場で使われた隠語──白豚・黒豚・代用豚
映画の中で語られる、あまりに不穏な言葉がある。
- 白豚(しろぶた)
→ 白人(米兵)を指す隠語 - 黒豚(くろぶた)
→ 現地人を指す隠語 - 代用豚(だいようぶた)
→ 日本兵を指す隠語
これらは、映画的誇張でも、奥崎の妄想でもない。実際に戦場で使われていたと複数証言される言葉であり、戦争末期の日本陸軍内部で“意味が共有されていた隠語”である。
大阪で店をやっている元衛生兵を問い詰めた際に、「人肉を食べていたことは当たり前だから、それだけで罰せられることはない。日本兵だって食べたが、殺してまでは食べない。死んだら食べていただけ」という内容の証言があった。
なぜ「処刑」と「人肉食」は結びつくのか
奥崎謙三が問い続けるのは、ここだ。
- なぜ兵士は殺されたのか
- 本当に「軍律違反」だったのか
- それとも、食料確保のためではなかったのか
映画の中で示唆される構図は残酷だ。
処刑
↓
「処理」
↓
食料化
つまり、軍事的正義の名を借りた人肉食の隠蔽である。
奥崎はこれを、「戦場の極限状態」では済ませない。
原一男が決して否定しない点
重要なのは、監督・原一男がこの疑惑を否定も断定もしないことだ。
- 証言は食い違う
- 記憶は曖昧
- 嘘も混じる
それでもカメラは止まらない。
なぜなら、この映画の本質は「事実の確定」ではなく「問いの持続」だからだ。
人は、どこまで追い詰められれば
他人を食料として合理化できるのか。
戦後日本が最も触れたくなかったテーマ
日本では長らく、「日本兵=被害者」という物語が共有されてきた。
だが人肉事件は、その構図を完全に破壊する。
- 加害と被害の境界が消える
- 正義と狂気が溶け合う
- 国家が沈黙を選ぶ
奥崎謙三は、この沈黙そのものを許さなかった。
人肉事件を追う奥崎は「狂っている」のか?
多くの観客はこう感じる。
そこまでやる必要があるのか
もう終わった戦争じゃないか
だが、映画は問い返す。
終わったことにしたのは、誰なのか?
人肉事件とは、「戦争が人間をどこまで壊すか」の極限例であるが実際に起こっていたことであり、それを直視しない限り、戦争は思想や理想や感情など「抽象的悲劇」に矮小化されてしまうのだ。この一点だけでもこの映画には、「本当の戦争はそんなもんじゃない」という強烈なメッセージがある。
この映画が地上波で放送しづらい本当の理由
『ゆきゆきて、神軍』が今なお扱いづらい理由は明白だ。
- 天皇制批判
- 私刑と暴力
- そして 人肉食という最終タブー
これは倫理の問題以前に、国家の物語が崩壊するからである。
人肉事件は“異常”ではなく“構造”だった
- 人肉食は一部の狂人の行為ではない
- 極限状況と命令体系が生んだ「構造的犯罪」
- 奥崎謙三は、それを「個人の顔」に引き戻した
『ゆきゆきて、神軍』は、ただの戦争映画ではない。
人間が「ここまでやってしまう」ことを、観客自身に引き受けさせる映画である。
まとめ|この映画は、観客(日本人)を裁く
本作は海外で高く評価された一方、日本では長く上映・配信が困難だった。
- 暴力描写
- 天皇制批判
- 倫理的に危うい手法
それでも本作は、「見なかったことにできない映画」として語り継がれている。
『ゆきゆきて、神軍』は問いかける。
あなたは、何を見なかったことにして生きているのか?
この映画を観終えたあと、何も感じなければ、それこそが最も恐ろしい。
ゆきゆきて、神軍が突きつけた「人肉事件」は、単なる戦場の異常事例ではない。それは、極限状況の中で人間が倫理を合理化し、組織が責任を曖昧にし、戦後社会が沈黙を選んできた構造そのものを映し出している。白豚・黒豚・代用豚という言葉が示すのは、命が言葉によって処理され、記録から消されていく過程だった。
この映画が今なお「問題作」であり続ける理由は明確だ。戦争を過去の悲劇として消費することを拒み、観る者自身に「見なかったことにしてきた責任」を引き受けさせるからである。人肉事件の真偽を超えて残るのは、問いを終わらせないことの重さだ。
『ゆきゆきて、神軍』は答えを与えない。だが、問いから逃げる自由も与えない。それこそが、この作品が封印され、同時に語り継がれる理由である。
現在、ゆきゆきて、神軍は、Amazonプライムビデオで400円で観ることが出来る。ただし、日本映画NETに登録すれば14日間の無料体験で無料で観ることも可能である。核兵器保有論争が起きるような戦争の記憶が消えている現代日本人に、この機会に、是非、観てほしい。